こんにちは、HALです。
営業職で転職を考えている人の中には「転職のタイミングはいつがベスト?」「営業から転職できる業界は?」 と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
営業職は成果主義の企業が多く、ボーナスやインセンティブの影響を受けやすい仕事です。そのため、転職のタイミングを誤ると、思わぬ収入減やキャリアの停滞につながる可能性があります。タイミングの見極め方は人それぞれ異なりますが、市場の動向や退職の準備を理解し、計画的に進めることが成功のカギとなります。
本記事では、営業職の転職に最適なタイミングを詳しく解説し、転職成功のポイントや退職までの流れも紹介しています。転職を考えている方は、ぜひ本記事を参考に、後悔のない決断をしてください。今があなたのキャリアを見直す絶好のタイミングかもしれません。
● 営業職が転職するベストなタイミングとその理由を理解できる
● 転職の判断基準や適切な見極め方を学べる
● スムーズに退職するための具体的な流れを知ることができる
● 転職成功のために必要な準備やポイントを把握できる
*本ページはプロモーションが含まれています
「今の会社に少しでも不満がある」「年収アップしたい」「ブラックから抜け出したい」…そんな方にはまずは気軽に転職活動してみることを強くおすすめします。
転職エージェントや転職サイトは無料で利用できますし、良い企業が見つからなければ活動を辞めるのも全然アリです。自分の市場価値を知り、キャリアの幅を広げることが重要です。
当サイトでは多数あるサービスから厳選したおすすめの転職エージェントや転職サイトをまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
\ 転職活動の第一歩!気軽に無料登録! /
\ 自分のペースで進めたい人向け! /
営業が転職するベストなタイミングとは?
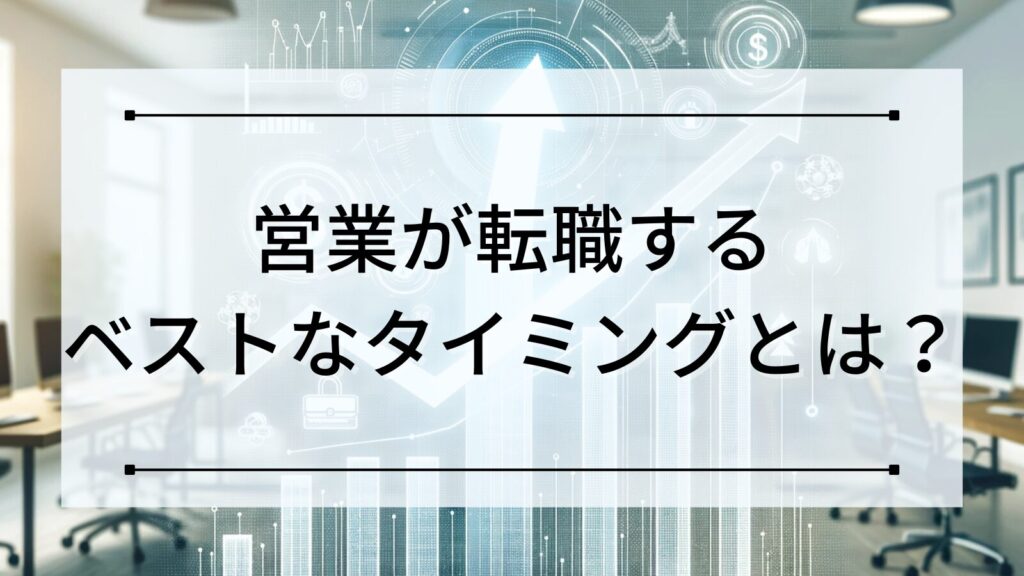
営業職として働いていると、「いつ転職するのがベストなのか」と悩むことがあるでしょう。タイミングを誤ると、転職後のキャリアや収入に大きな影響を与える可能性があります。
特に営業職は業務の繁忙期やインセンティブの影響が大きいため、適切なタイミングを見極めることが重要です。ここでは、営業が転職する際に最適なタイミングを4つ紹介します。
ボーナスを貰ったあと
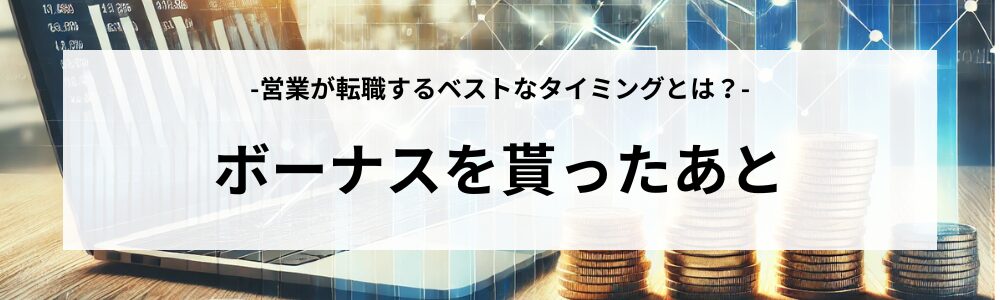
ボーナス支給後に転職を考えるのは、多くの営業マンにとって合理的な選択でしょう。ボーナスを受け取った後に退職することで、経済的な余裕を持ちながら転職活動を進められるからです。
ボーナスを受け取るメリット
ボーナスは会社の業績や個人の成績に応じて支給されるため、できるだけ満額受け取るのが賢明です。特に営業職は成果に応じたインセンティブが含まれていることが多く、退職前にしっかりと受け取っておくことで、次のステップへの準備資金として活用できます。ボーナス支給直後に退職の意向を伝えることで、会社への影響も最小限に抑えられます。
注意点
ただし、ボーナスをもらった直後に退職の意向を伝えると、「ボーナスだけ受け取って辞めた」と悪印象を持たれることもあります。円満退職を目指すなら、ボーナス支給後、1〜2週間ほど経過してから退職の意向を伝えるのがベターです。また、次の転職先がすでに決まっている場合は、転職先の入社タイミングとボーナスの支給日をうまく調整する必要があります。
営業マンとして限界を感じたとき
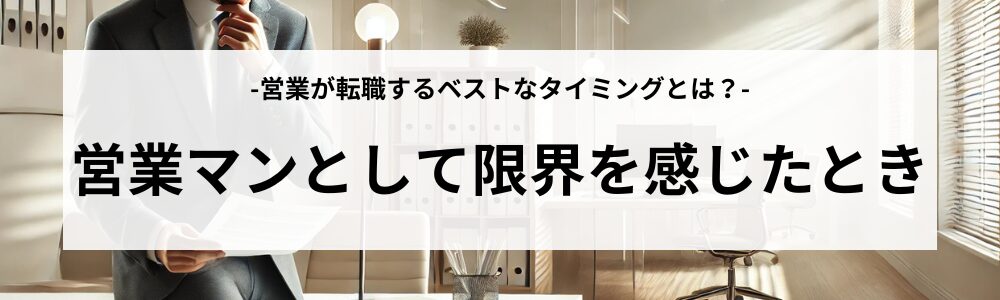
営業職は高い成果を求められる仕事です。そのため、精神的・肉体的に限界を感じた場合は、早めに転職を検討するべきです。無理を続けることで心身の健康を損ない、キャリアにも悪影響を及ぼす可能性があるからです。
精神的・肉体的な負担が大きい場合
営業職はプレッシャーの大きい仕事です。特にノルマが厳しい環境では、数字に追われるストレスが蓄積しやすくなります。「上司や同僚との関係が悪い」「休みが取れない」「長時間労働が常態化している」といった場合、我慢を続けることで燃え尽き症候群に陥ることもあります。
転職を決断するサイン
以下のようなサインがある場合、転職を真剣に考えるべきです。
- 出社前に強い憂鬱を感じる
- 仕事のモチベーションが完全になくなった
- 営業活動が辛すぎて体調を崩している
- 上司や同僚と話すのが苦痛になってきた
- 仕事の成果が出ないにもかかわらずサポートがない
特に、精神的な負担が大きく、日常生活にまで支障をきたすようになった場合は、すぐに退職の準備を進めましょう。体調を崩してからでは、転職活動すら難しくなることもあります。
閑散期
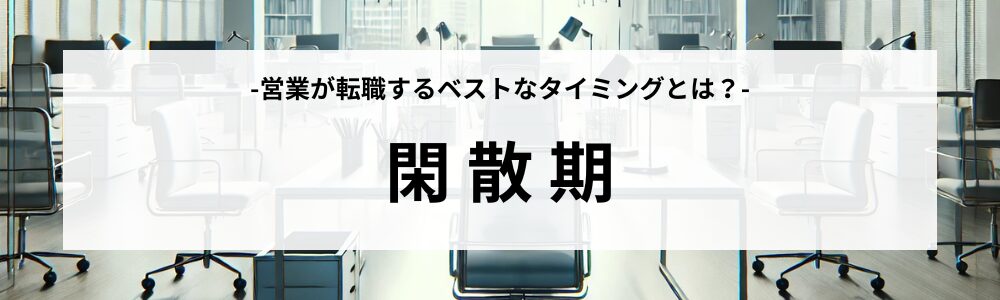
営業職は業界によって繁忙期と閑散期が異なります。会社が比較的落ち着いている閑散期に退職を申し出ることで、引継ぎがスムーズになり、円満退職しやすくなるのがメリットです。
なぜ閑散期が良いのか?
閑散期に退職を申し出ると、引継ぎに十分な時間を確保でき、後任への負担も軽減されます。特に営業職は担当顧客が決まっていることが多いため、顧客への挨拶や業務の引継ぎをしっかりと行うことで、後任がスムーズに仕事を進められるようになります。
閑散期の見極め方
業界によって閑散期は異なりますが、以下のようなタイミングが一般的です。
- 不動産業界
繁忙期は3〜4月(引越しシーズン)。閑散期は5〜6月、10〜11月 - 金融業界
決算時期の3月・9月は忙しいため、それ以外の時期が閑散期 - 小売・サービス業
年末年始やセール時期が繁忙期なので、それ以外の時期が狙い目
営業職として円満に退職したい場合は、自分の業界の閑散期を見極め、退職の意向を伝えるのがベストです。
年末
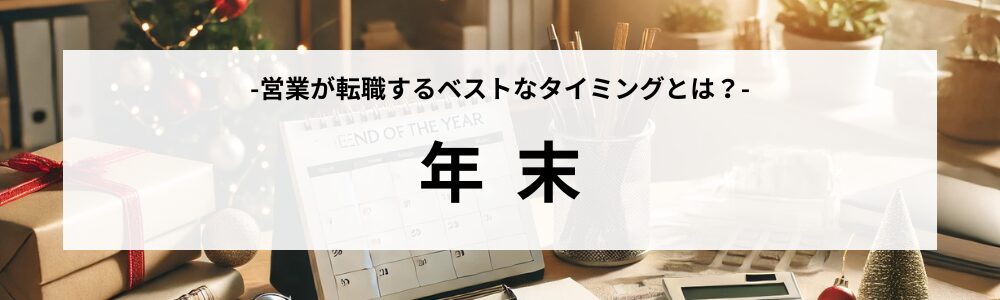
年末は、営業職にとって転職のタイミングとして最適な時期の一つです。企業の決算や人事異動の時期が重なるため、転職市場も活発になりやすいからです。
年末退職のメリット
1月〜3月は新年度に向けて多くの企業が中途採用を強化する時期です。そのため、年末に退職し、年明けからの転職活動に備えることで、より多くの求人の中から理想の転職先を見つけやすくなります。また、年末は人事異動や新しい体制が決まる時期でもあるため、組織の変化に伴って退職しやすい環境が整うこともあります。
年末退職の注意点
ただし、年末に退職する場合は、以下の点に注意が必要です。
- 12月のボーナス支給前に退職すると損をする可能性がある
- 年末年始は企業も休みに入るため、転職活動のスケジュールが立てにくい
- 年内に引継ぎを終えないと、年始から業務が混乱する恐れがある
そのため、12月初旬までには退職の意向を伝え、ボーナスを受け取った後に正式に退職するのが理想的です。年明けからスムーズに転職活動を進めるためにも、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
営業職の転職は、タイミングが重要です。ボーナスを受け取った後に経済的な余裕を持って転職するのも良いですし、限界を感じた時に無理をせず退職するのも大切です。さらに、閑散期を活用することで円満退職しやすくなり、年末に退職することでスムーズな転職活動につなげることもできます。
どのタイミングが最適かは個人の状況によりますが、自分にとってベストな時期を見極め、計画的に転職を進めることが成功の鍵となるでしょう。
今辞めても良いのかの見極め方
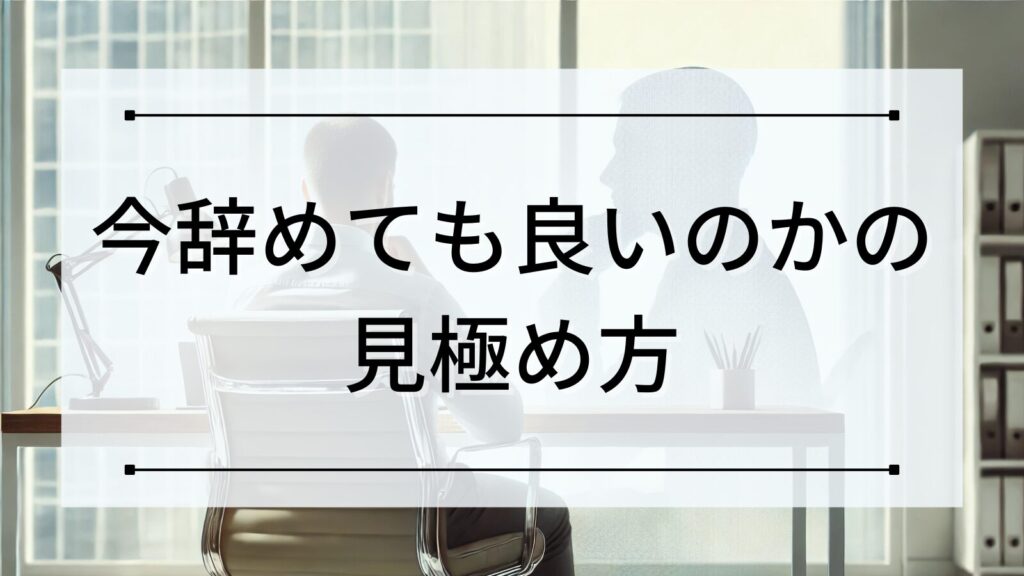
転職を考えているものの、「今本当に辞めてもいいのか?」と不安に感じる人は多いでしょう。営業職はノルマのプレッシャーや長時間労働など、厳しい環境で働くことも多いため、限界を感じて転職を考えるケースも少なくありません。
しかし、感情的に辞めてしまうと、次の職場でも同じ悩みに直面する可能性があります。そのため、自分の状況を冷静に分析し、転職すべきかどうかをしっかり見極めることが大切です。ここでは、転職のタイミングを見極めるためのポイントを解説します。
転職理由を明確にする
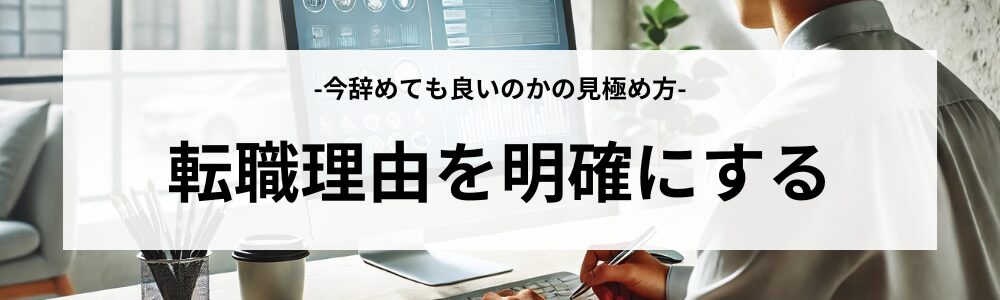
転職を成功させるためには、まず「なぜ転職したいのか?」を明確にすることが重要です。漠然と「辞めたい」と考えるだけでは、転職後に同じ悩みを抱える可能性が高まります。理由を整理することで、自分にとって本当に必要な転職なのかを判断しやすくなります。
転職理由の整理方法
転職理由を整理する際は、以下のような項目をチェックしましょう。
- 職場環境の問題(長時間労働・パワハラ・人間関係)
- 営業職そのものが向いていないと感じる
- 成果が給与に反映されない
- ノルマのプレッシャーが強すぎる
- もっと違う業界・職種で活躍したい
例えば、「ノルマが厳しくてストレスが大きい」という場合、転職することで解決するのか、それとも企業を変えずに異動を希望することで解決できるのかを考える必要があります。
転職で解決できる問題かを考える
営業職を辞めたい理由が「ノルマが厳しい」「給与が低い」「人間関係が悪い」などの場合、転職が解決策になるケースもあります。ただし、「どの企業に転職しても営業職にはノルマがある」「どの職場でも人間関係の悩みは生じる可能性がある」といった点も考慮しなければなりません。
転職によって解決できる問題なのか、それとも今の職場で改善の余地があるのかを見極めることが重要です。例えば、営業ノルマのプレッシャーが強すぎる場合、「インサイドセールス」や「反響営業」など、ノルマの厳しくない営業職へ転職するという選択肢もあります。
体調やメンタルの状態をチェックする
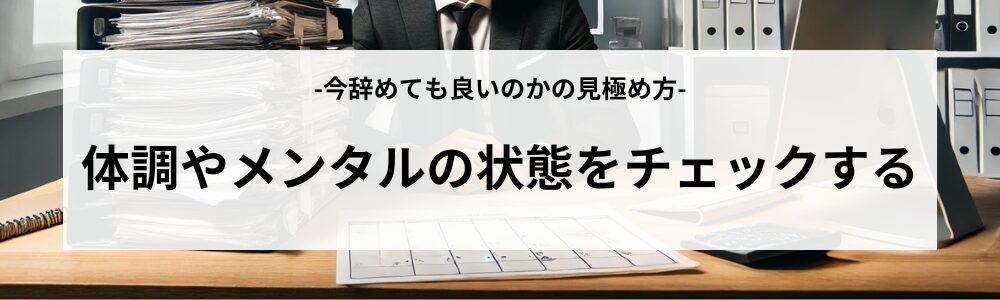
営業職の仕事が原因で心身に不調を感じている場合は、早めに対処する必要があります。体調を崩してしまってからでは、転職活動どころではなくなる可能性もあるため、無理をしないことが大切です。
ストレスや体調不良のサイン
以下のような症状が続いている場合は、注意が必要です。
- 毎朝、会社へ行くのが憂鬱で仕方がない
- 仕事のことを考えると動悸がする
- 頭痛や胃痛、不眠などの症状が続いている
- 休みの日でも仕事のことが気になってしまう
- 職場での人間関係に強いストレスを感じる
このような症状が長期間続く場合、精神的な負担が限界に達している可能性があります。無理をしすぎると、うつ病や適応障害といったメンタルヘルスの問題に発展することもあるため、早めに休養や転職を検討することが大切です。
健康を優先して転職を検討する
仕事によるストレスが原因で体調を崩している場合は、転職先を決める前に休職を考えるのも一つの方法です。また、無理に続けるのではなく、転職エージェントに相談しながら自分に合った環境を探すのも良いでしょう。
退職後のキャリアプランを考える

転職を決断する前に、現職から今後のキャリアプランをしっかりと考えておくことが重要です。単に「今の仕事を辞めたい」という気持ちだけで行動すると、転職後に「思っていた環境と違う」「やりたいことが見つからない」といった問題に直面することがあります。
転職は人生の大きな分岐点となるため、退職後のビジョンを明確にしておくことが必要です。
どの業界・職種を目指すのかを明確にする
退職を考えている段階で「自分は何をやりたいのか」「なぜ転職したいのか」を具体的に考えることが重要です。営業職で培ったスキルを活かして、同じ営業職でより良い条件の企業を目指すのか、それとも異業種・異職種にチャレンジするのかを明確にしましょう。
例えば、営業経験を活かせる職種として、マーケティングやコンサルティング、人事などが挙げられます。これらの職種では、交渉力や提案力といった営業スキルが活かせるため、スムーズにキャリアチェンジしやすい傾向にあります。
転職市場の状況をリサーチする
転職活動を始める前に、現在の転職市場の状況をリサーチしておきましょう。求人数が多い時期や、成長産業などを把握することで、転職の成功率を高めることができます。特に、営業職の経験が評価されやすい業界や企業を見つけることがポイントです。また、転職エージェントを活用することで、自分に合った求人情報を効率的に収集することが可能になります。
このように、退職後のキャリアプランを明確にすることで、転職を成功させるための土台を作ることができます。焦らずに、しっかりと準備を進めましょう。
20代と30代の違い
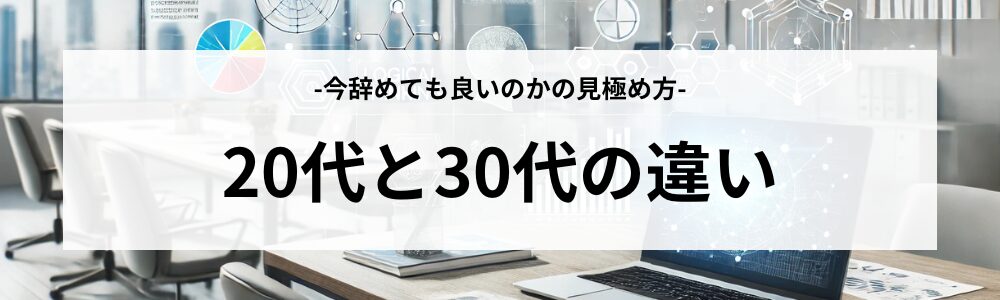
営業職の転職市場では、20代と30代で求められるスキルや転職の難易度が異なります。そのため、自分の年齢に応じた戦略を立てることが大切です。
20代の営業マンの転職の特徴
20代の営業マンは、未経験の業種や職種に転職しやすい傾向があります。特に第二新卒(入社1〜3年以内)の場合、「ポテンシャル採用」として、スキルや経験よりも意欲や将来性を重視されることが多いです。
また、営業職の経験は他の職種に生かしやすいため、マーケティング、企画、カスタマーサクセスなどの職種への転職も選択肢になります。20代のうちにキャリアチェンジをする場合は、「どの職種に興味があるのか」「どんなスキルが必要なのか」を事前に調査し、必要な準備をしておくことが重要です。
30代の営業マンの転職の特徴
30代になると、企業は即戦力としてのスキルや経験を求める傾向にあります。20代のようにポテンシャル採用の枠が比較的少なくなるため、「実績」や「マネジメント経験」が問われる場面が増えてきます。
営業が転職する(職場を退職する)際の最適な流れ
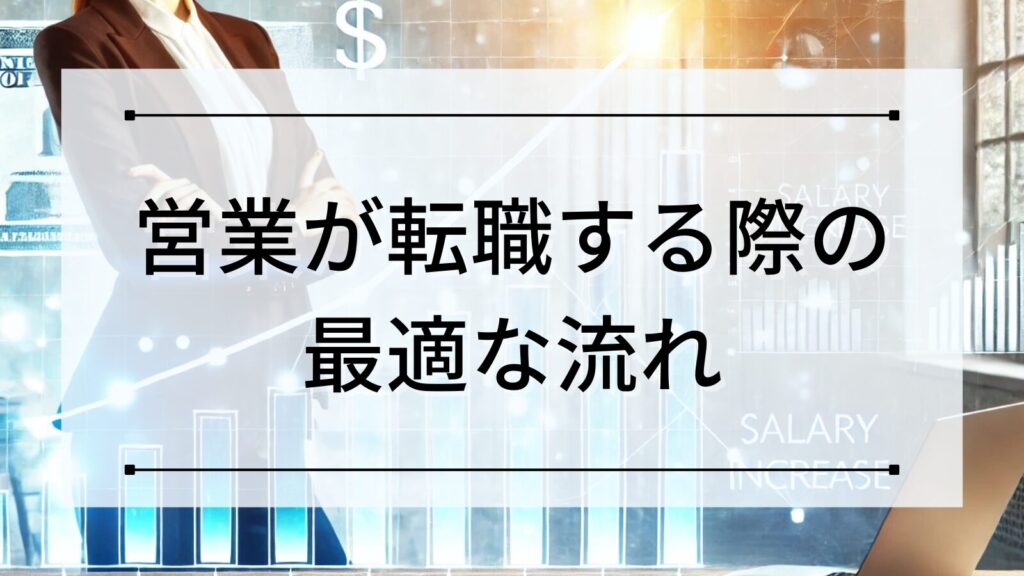
営業職から転職を考えたとき、スムーズに退職するためには適切なステップを踏むことが重要です。特に営業職は、顧客対応や売上目標などの責任が大きいため、計画的に退職準備を進めなければなりません。
焦って退職を進めると、円満退社が難しくなり、次の職場にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、営業が転職を成功させるための適切な退職の流れを解説します。
次の就職先を決める
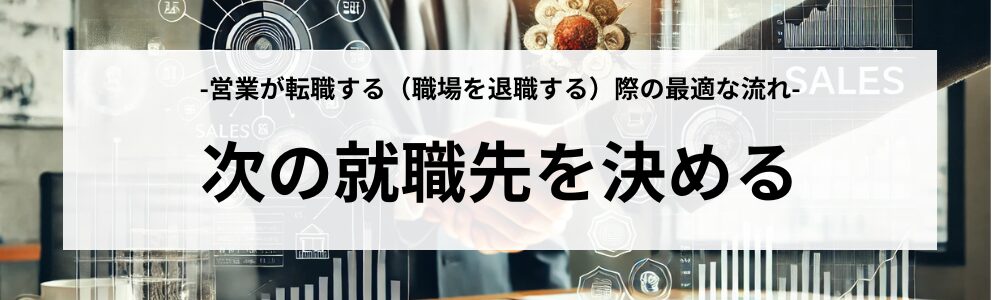
転職を決意した場合、まず最初にすべきことは次の就職先を決めることです。勢いで退職してしまうと、無職の期間が長引き、経済的にも精神的にも負担がかかるため、慎重に転職活動を進めましょう。
転職先を決めてから退職すべき理由
営業職は即戦力を求められる職種のため、転職活動では自分のスキルや実績を明確にアピールする必要があります。特に、未経験の業界や職種へ転職する場合は、スムーズに転職するために事前の準備が欠かせません。
また、退職後に焦って転職活動を進めると、妥協して企業を選んでしまい、「転職先が合わなかった」と後悔する可能性もあります。そのため、転職活動は在職中に行い、内定を確保してから退職するのが理想的です。
転職活動を効率的に進める方法
転職活動を始める際には、転職サイトや転職エージェントを活用すると効率的に進めることができます。特に転職エージェントは、自分に合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書の添削や面接対策などのサポートも提供してくれるため、忙しい営業職でもスムーズに転職活動を進めることができます。
さらに、転職市場の動向を把握することも重要です。業界によっては求人数が増える時期があるため、転職のタイミングを見極めて動くことで、より良い条件の企業に転職しやすくなります。
最低でも1ヶ月前には退職の意志を伝える
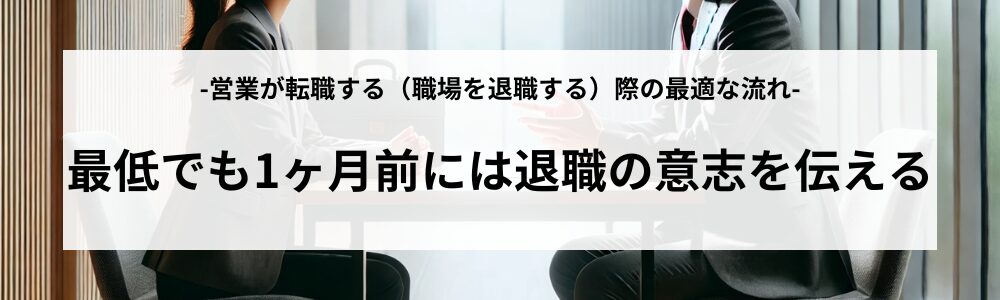
転職先が決まったら、次にすべきことは退職の意志を上司に伝えることです。退職は、会社の業務に大きな影響を与えるため、最低でも1ヶ月前には伝えるようにしましょう。
退職を伝える際の注意点
営業職は顧客対応や売上目標の達成に直接関わるため、急な退職は会社にとって大きな負担となります。可能であれば、退職の2〜3ヶ月前には上司に相談し、スムーズに引き継ぎができるように調整するのが理想的です。
また、退職を伝える際には、感情的にならず、冷静に話すことが重要です。「今の会社が嫌だから辞める」という言い方ではなく、「キャリアアップのために新しい環境で挑戦したい」といった前向きな理由を伝えると、円満に退職しやすくなります。
退職を伝えるタイミング
退職を伝えるタイミングは、会社の繁忙期や営業目標の締め日を考慮することが大切です。例えば、営業職の場合、四半期や年度末にあたる時期は忙しくなるため、そのタイミングで退職を申し出ると、引き継ぎが難しくなってしまいます。退職を考えている場合は、業務が落ち着く時期を見極めて伝えるようにしましょう。
退職届を提出する
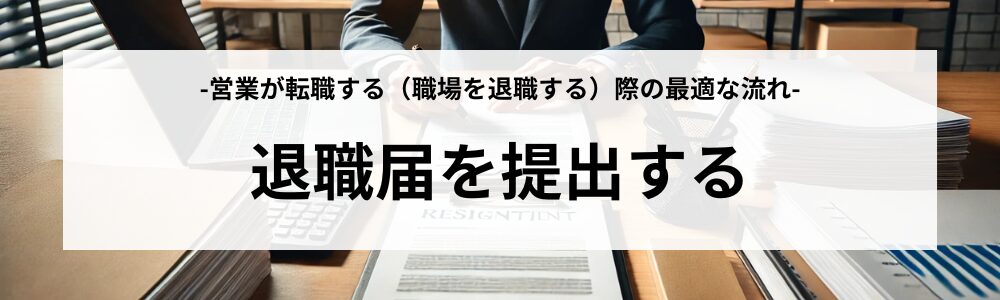
退職の意志を伝えた後は、正式に退職届を提出する必要があります。退職届を提出することで、会社との退職手続きが正式に進められるため、適切なタイミングで提出することが重要です。
退職届の提出タイミング
退職届は、退職の意志を伝えた後に会社から提出を求められることが一般的です。会社の規定によっては、退職届の提出時期が決められている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
また、退職届と退職願は異なるものです。退職願は「退職を希望する」旨を伝える書類であり、会社側が承認しなければ退職できません。一方で、退職届は「退職を確定させる」ための書類であり、受理されれば退職が決定します。
退職届の書き方
退職届を作成する際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 書式はシンプルに
退職届には、以下の内容を明記します。- 退職理由(「一身上の都合により」と記載するのが一般的)
- 退職日
- 提出日
- 自分の氏名と押印
- 宛名(直属の上司または会社の代表者)
- 手書きが基本
会社の規定によりますが、一般的には手書きで提出するのがマナーとされています。ただし、最近ではパソコンで作成しても問題ないケースもあるため、事前に会社のルールを確認しておきましょう。 - 提出方法に注意
退職届は、直属の上司に手渡しするのが一般的です。メールや郵送ではなく、直接手渡しすることで、誠意を伝えることができます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、郵送での提出が認められることもあります。
引き継ぎをする
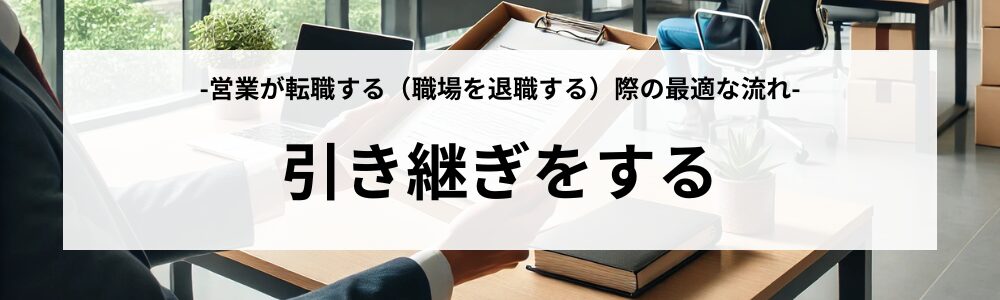
退職する際、営業職において最も重要なステップの一つが引き継ぎです。営業職は顧客との関係性が重要であり、適切な引き継ぎができていないと取引先の信頼を失い、会社に悪影響を与える可能性があります。円満に退職するためには、スムーズな引き継ぎを心掛けましょう。
引き継ぎの計画を立てる
引き継ぎは、単に情報を共有するだけではなく、後任者が円滑に業務を進められるようにすることが目的です。そのためには、計画的に進めることが大切です。具体的には、以下のような流れで準備を行いましょう。
- 取引先のリストを整理する
- 商談の進捗状況をまとめる
- 重要なクライアントの特徴や対応方法を記録する
- 自分が担当していた業務のマニュアルを作成する
これらの準備を進めておくことで、後任者がスムーズに業務を引き継ぐことができます。
取引先への対応
営業職の引き継ぎでは、取引先との関係を損なわないように配慮することが不可欠です。特に、長年築いてきた信頼関係がある場合、突然の担当変更により取引先が不安を感じることもあります。
そのため、以下のような対応を心掛けましょう。
- 取引先に直接挨拶を行い、担当変更について説明する
- 後任者を紹介し、円滑な引き継ぎができるよう支援する
- 可能であれば、取引先との打ち合わせに後任者を同席させる
このような対応をすることで、取引先との関係を維持しつつ、後任者がスムーズに業務を引き継げるようになります。
社内業務の引き継ぎ
営業職は外部の取引先との関係だけでなく、社内の業務も多岐にわたります。顧客情報の管理や報告業務、営業戦略の共有など、会社にとって重要な情報を適切に引き継ぐことが必要です。
社内業務の引き継ぎを行う際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 営業日報や過去の案件情報を共有する
- 使用していたツールやシステムの操作方法を説明する
- 他部署との連携方法や注意点を明確に伝える
特に、社内での連携が必要な業務については、後任者だけでなく関係者にも情報を共有しておくことが重要です。
有給を消化する
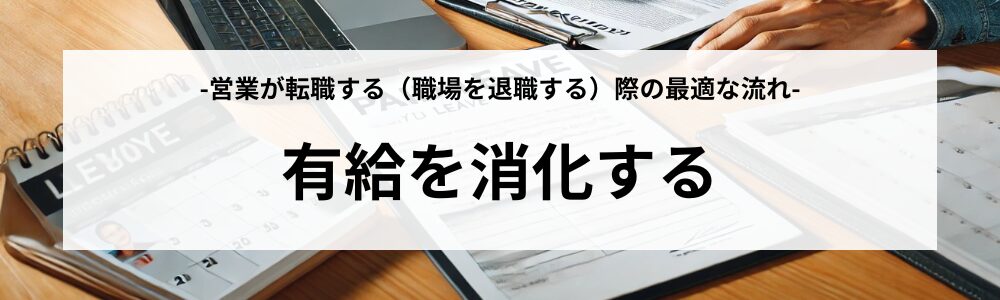
有給休暇は、働く人に与えられた権利であり、適切に取得することが推奨されます。退職時には、できるだけ有給を消化することが望ましいですが、会社の状況に配慮しながら進めることが大切です。
退職前の有給取得のルールを確認する
会社によっては、有給休暇の消化についてルールが決められていることがあります。例えば、「退職前に有給をすべて消化することが認められている場合」や「一部しか取得できない場合」など、企業ごとに異なります。
退職前に有給を取得する場合、以下の点を確認しておきましょう。
- 会社の就業規則に有給休暇消化のルールが明記されているか
- 退職日までにどの程度の有給が残っているか
- 退職前にどのタイミングで有給を取得できるか
事前に上司や人事部と相談し、トラブルにならないように手続きを進めることが重要です。
有給消化の計画を立てる
有給休暇をスムーズに消化するためには、計画的に取得することが大切です。特に、引き継ぎ期間と重ならないように注意し、適切なタイミングで申請を行いましょう。
有給取得の計画を立てる際には、以下の点を考慮するとよいでしょう。
- 引き継ぎが完了するタイミングを考慮する
- 会社の繁忙期を避ける
- 事前に上司と調整しておく
こうすることで、円満に有給を消化しながら退職準備を進めることができます。
有給が取得しにくい場合の対応
一部の企業では、有給休暇を取得しづらい雰囲気がある場合もあります。そのような場合でも、有給を申請する権利は労働者にあるため、適切に活用しましょう。
もし、有給取得を拒否されるような場合には、以下の対応を検討するのも一つの方法です。
- 退職日を調整し、有給を含めたスケジュールを提案する
- 会社の人事部門に相談し、適切な手続きを進める
- やむを得ない場合は、法的な手段を検討する
有給消化をめぐるトラブルを避けるためにも、事前にルールを確認し、計画的に申請することが重要です。
退職する
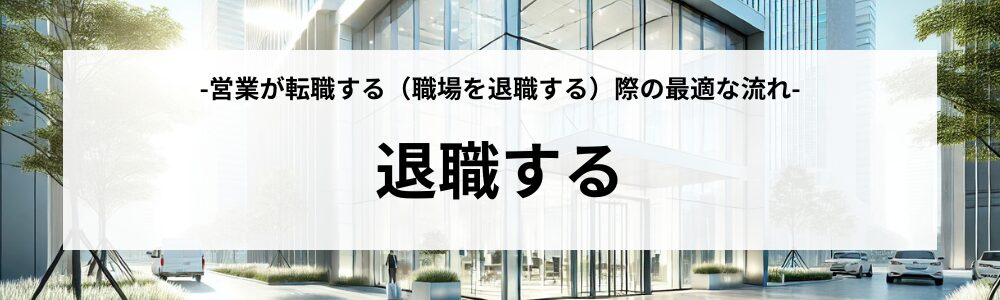
退職の最終ステップでは、会社への感謝を伝えながら、円満に職場を去ることが大切です。最終出社日までしっかりと準備を行い、気持ちよく新しい環境へ進みましょう。
最終出社日に行うこと
最終出社日には、以下のような準備を行いましょう。
- デスクやロッカーの整理を行い、私物を持ち帰る
- 会社から支給されているPCやスマートフォン、IDカードを返却する
- 退職時の書類(退職証明書など)を受け取る
- 最後の挨拶をする
特に、同僚や上司、取引先への挨拶を忘れずに行い、これまでの感謝を伝えることが大切です。
退職後の手続き
退職後には、いくつかの手続きが必要になります。例えば、健康保険や年金の切り替え、退職金の受け取り、税金の手続きなどがあります。スムーズに新しい環境へ移行するためにも、必要な手続きを確認しておきましょう。
退職後の主な手続きには、以下のようなものがあります。
- 健康保険の切り替え(国民健康保険 or 家族の扶養に入る)
- 年金の手続き(国民年金への加入 or 転職先での手続き)
- 退職金や企業年金の受け取り手続き
退職後の生活をスムーズにスタートさせるために、これらの手続きを忘れずに行いましょう。
営業マンの転職は難しい?
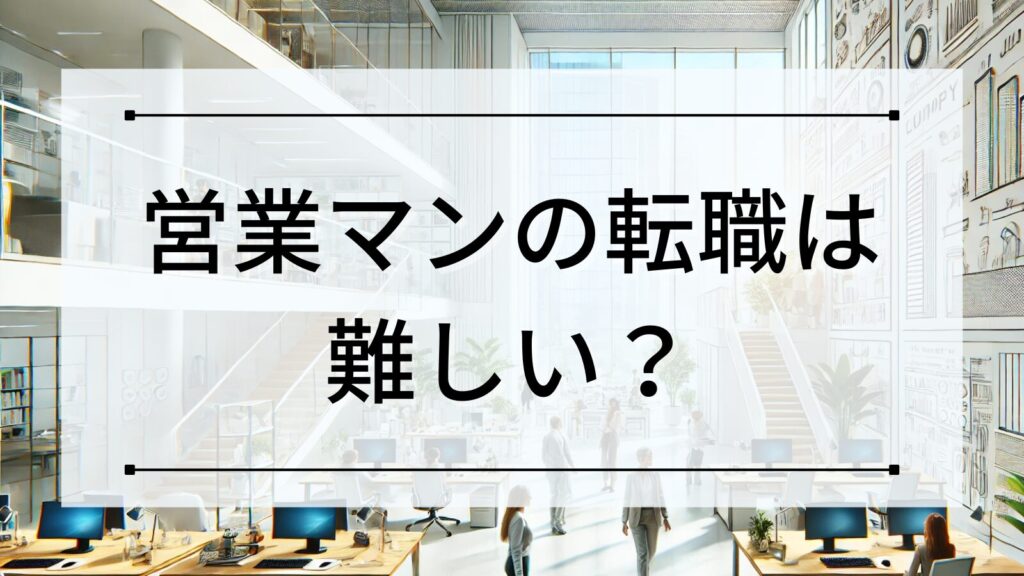
営業職の転職は「難しい」と言われることもありますが、実際のところはケースバイケースです。
営業職は多くの業界で求められる職種であり、経験やスキルを活かせば転職のチャンスは多いと言えます。しかし、一方で注意しなければならないポイントも存在します。ここでは、営業職の転職が難しくなる要因と、成功させるためのポイントについて解説します。
営業職の転職が難しいと感じる理由

営業職の転職が難しくなるケースはいくつか考えられます。特に、以下のような理由で転職活動が思うように進まないことがあります。
業界や職種のミスマッチ
営業職は「つぶしがきく」と言われることが多いですが、業界や職種が大きく異なると転職が難しくなる場合があります。特に、金融や不動産などの専門知識が求められる業界では、未経験の業界に転職しようとするとハードルが高くなりがちです。
例えば、法人向けの無形商材を扱っていた人が、個人向けの有形商材(自動車販売など)の営業職へ転職する場合、求められるスキルや営業スタイルが大きく異なるため、適応に時間がかかることがあります。
転職回数が多いと敬遠される
営業職は成果主義の企業が多いため、実績が重視されます。しかし、転職回数が多いと「長く続かないのでは?」と懸念され、書類選考で落とされることもあります。
特に、短期間での転職を繰り返している場合、企業側は「すぐに辞めるリスクがある」と判断し、採用を見送ることもあります。そのため、転職の際には「なぜ転職を考えているのか」「今回の転職でどのようなキャリアを築きたいのか」を明確にすることが重要です。
30代以降は即戦力を求められる
20代の営業職であれば、ポテンシャル採用として未経験の業界でも採用される可能性が高いですが、30代以降は比較的即戦力としてのスキルが求められる傾向にあります。特に、管理職経験のない30代後半以降の営業マンは、「マネジメント経験がない」と判断され、転職の選択肢が狭まることもあります。
このため、30代以降で転職を考える場合は、業界の専門知識を深めたり、マネジメント経験を積んでおくことが転職成功のカギとなります。
営業職の転職を成功させるためのポイント
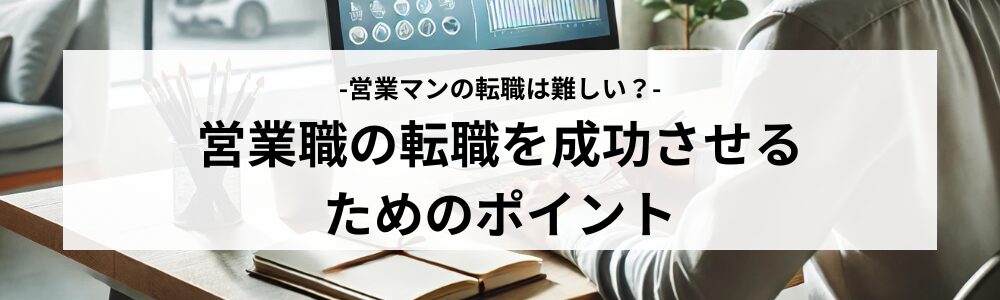
営業職の転職が難しくなる要因を理解した上で、成功させるためのポイントを押さえておきましょう。
自分の強みを整理し、適切にアピールする
営業職は「人と話すのが得意だからできる仕事」と思われがちですが、実際には論理的思考力や課題解決力、プレゼンテーション能力など、幅広いスキルが求められます。特に転職活動では、「どのような営業スタイルで、どんな成果を出してきたのか」を具体的に伝えることが重要です。
例えば、以下のように整理すると、自分の強みが明確になります。
- 過去の営業実績(売上や新規顧客獲得数)
- 得意な営業手法(飛び込み営業、ルート営業、インサイドセールスなど)
- 具体的な成功事例(どのような課題を解決し、どんな結果を出したか)
これらの情報を面接で的確に伝えることで、採用担当者に自分の実力をアピールできます。
なお、転職時の自己PRについては別の記事で詳しく解説しているため、よろしければ併せてチェックしてください。

転職市場のニーズを把握する
営業職の求人は業界によって大きく異なります。例えば、SaaS(クラウドサービス)やDX(デジタルトランスフォーメーション)関連の企業は、積極的に営業職を募集しています。一方で、従来型の営業手法が主流の業界では、営業スキルよりも業界経験や人脈が重視されることがあります。
このため、自分の経験がどの業界で活かせるのかを分析し、転職市場の動向を把握することが大切です。転職エージェントを活用すれば、最新の求人情報を得ることができ、自分に合った応募先を見つけやすくなるでしょう。
在職中に転職活動を進める
転職を考えている場合、「まず会社を辞めてから転職活動をする」というのはリスクが大きいです。営業職は業務が忙しいため、転職活動に時間を割くのが難しいこともありますが、在職中に少しずつ情報収集を進めることが重要です。
在職中に転職活動をすることで、焦らずに企業選びができ、より良い条件で転職を成功させることが可能になります。
人脈を活かす
営業職は人脈が強みとなるケースが多いため、過去に関わった取引先や同僚の紹介を活用するのも一つの方法です。特に、業界内での転職を考えている場合は、信頼できる人脈を活かして情報を集めることで、より有利に転職活動を進められます。
また、転職エージェントを活用することで、業界の最新情報を収集しながら、自分に合った求人を見つけることができます。
営業職の転職は「難しい」より「戦略が重要」
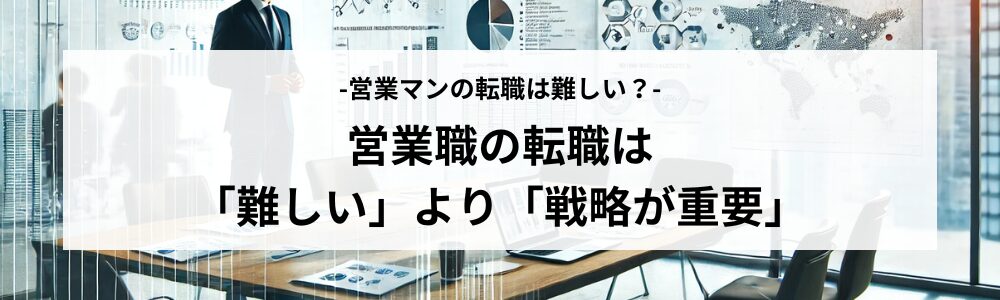
営業職の転職は、一見すると難しく感じるかもしれません。しかし、適切な準備と戦略を立てることで、転職の成功率を大きく高めることができます。業界や職種の選び方、自己アピールの方法を工夫すれば、より良い企業への転職を実現することも十分可能です。
転職を成功させるためには、自分の経験や強みを整理し、どのようにキャリアを築いていきたいのかを明確にすることが大切です。営業職としての経験を最大限に活かしながら、自分に合ったキャリアを見つけていきましょう。
営業マンの次におすすめの業界は?
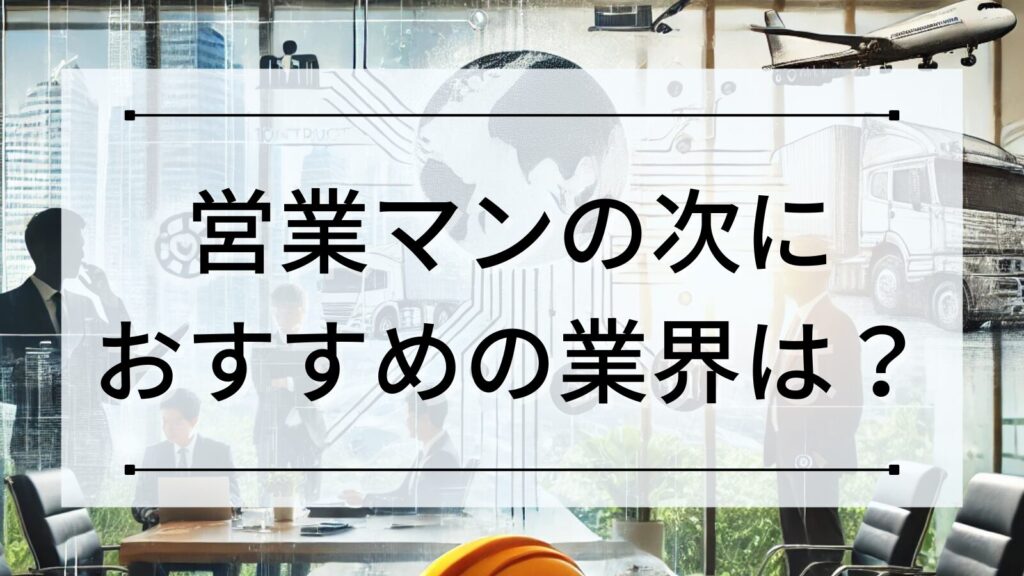
営業職は多くの業界で求められるスキルを身につけることができるため、転職先の選択肢は幅広いです。しかし、「どの業界に転職するのが最適なのか?」と悩む人も多いでしょう。
基本的には自身が気になっている・興味がある業界がおすすめですが、迷っている場合は営業職として培ったスキルを活かしやすく、キャリアアップにもつながる業界を選ぶのがおすすめです。ここでは、営業職からの転職に適した業界をいくつか紹介します。
IT・SaaS業界|成長市場で高収入を狙える

IT・SaaS業界は、デジタル化の進展に伴い、企業のニーズが急速に拡大している分野です。営業職のスキルを活かしつつ、より専門的な知識を身につけることで、年収アップやキャリアの可能性を広げられます。
IT・SaaS業界の特徴
IT・SaaS業界は、特に法人向けの営業職(BtoB営業)に適しており、専門的な知識を学ぶ意欲がある人には最適です。クラウドサービスやDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、企業の導入ニーズが高まっているため、営業職として活躍できる場面が増えています。
向いている人と求められるスキル
- 新しい技術やトレンドを学ぶことに意欲がある
- 論理的思考力やプレゼン能力が高い
- 顧客の課題を解決する提案営業が得意
特に、IT未経験者でも、学習意欲があれば転職成功の可能性は高いでしょう。
コンサルティング業界|営業経験を活かしつつ専門性を高める
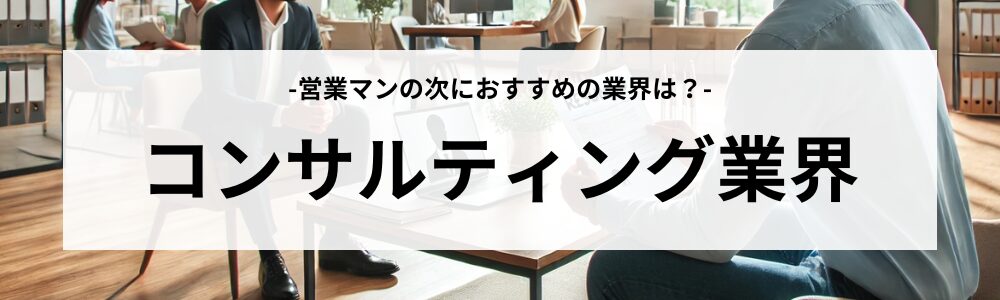
コンサルティング業界は、クライアント企業の経営課題を解決する仕事であり、営業職の経験を活かしながらキャリアアップが可能な業界です。
コンサルティング業界の魅力
法人営業で培った「課題解決力」「プレゼン能力」が活かせるのがコンサルティング業界の強みです。特に、クライアントとの関係構築力や提案力を持つ営業職経験者は、コンサルタントとしての適性が高いといえます。
コンサル業界で求められるスキル
- 論理的思考力と分析力
- クライアントの課題を深く理解する力
- 長期的な視点でビジネスを考えられる能力
ただし、コンサル業界は労働時間が長くなりやすい傾向があるため、ワークライフバランスを重視する場合は企業選びに注意が必要です。
人材業界|営業経験をダイレクトに活かせる

人材業界は、求職者と企業をつなぐ業務を担う業界であり、営業スキルをそのまま活かせる分野です。
人材業界の仕事内容
人材業界の営業には、主に以下の2種類があります。
- 企業向けの法人営業(求人開拓)
企業の採用ニーズを把握し、最適な人材を紹介する仕事です。法人営業の経験がある人は、比較的スムーズにキャリアチェンジできます。 - 求職者向けのキャリアアドバイザー
転職希望者のキャリア相談を行い、最適な求人を提案する仕事です。個人とのコミュニケーションが得意な人には向いています。
人材業界のメリットと注意点
人材業界は、営業経験を活かしつつ「人の人生に寄り添う仕事」ができる点が魅力です。ただし、求職者の状況に左右されることが多いため、成果が出るまで時間がかかることもあります。
不動産業界|高いインセンティブで収入アップを狙う

不動産業界は、成果報酬型のビジネスモデルが一般的であり、営業経験者が高収入を目指しやすい業界です。
不動産営業の種類
- 住宅販売・賃貸仲介
個人向けの営業が中心で、接客や提案力が求められる - 不動産投資営業
法人向けの営業で、専門知識を身につけることでキャリアアップ可能 - 商業不動産営業
オフィスビルや商業施設の取引を担当し、大規模な案件に関わる
注意点
不動産業界は、インセンティブが大きい分、競争が激しい傾向があります。また、土日出勤が多くなるため、ワークライフバランスを重視する人には向いていない可能性もあります。
金融業界|専門知識を身につけながら営業力を発揮
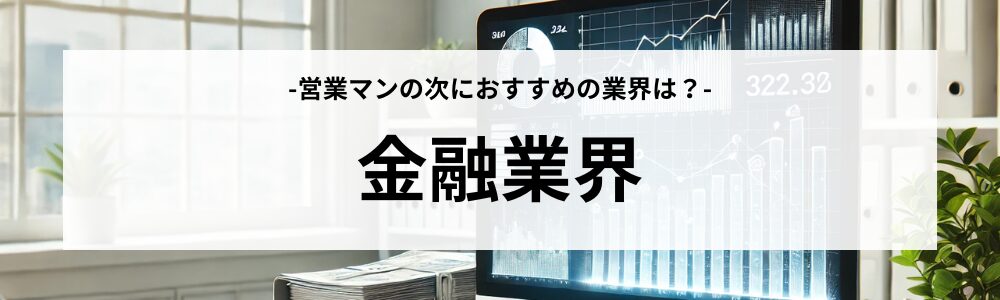
金融業界(銀行、証券、保険など)は、営業職の経験を活かしながら専門性を高められる業界の一つです。
金融業界の特徴
金融業界の営業は、専門知識を習得することで、長期的に安定したキャリアを築ける点が魅力です。特に、法人向けの資産運用提案や、富裕層向けの金融商品の販売は、営業スキルを活かしつつ高収入を狙えます。
金融業界で求められるスキル
- 顧客との信頼関係を築く力
- 数字に強く、論理的に説明できる能力
- 長期的な視点で提案できる力
ただし、証券や保険の営業では資格が必要になるケースが多いため、事前に取得の必要性を確認しておくことが重要です。
営業経験を活かせる業界を選ぼう
営業職からの転職は、選択肢が多いため「どの業界を選ぶべきか?」と迷うかもしれません。重要なのは、自分のスキルを活かしつつ、キャリアアップや収入アップが期待できる業界を選ぶことです。
営業経験を活かせるおすすめの業界
- IT・SaaS業界:成長市場で高収入が狙える
- コンサルティング業界:営業経験を活かしながら専門性を高める
- 人材業界:企業・求職者と関わる仕事で営業スキルを活用
- 不動産業界:インセンティブが大きく、成果が収入に直結
- 金融業界:専門知識を習得しながら長期的なキャリアを築く
どの業界に進むか決める前に、自分の強みを整理し、どのスキルを活かせるのかを考えることが成功のカギです。転職活動を進める際は、転職エージェントを活用しながら、自分に最適な業界を見つけましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか。以下にこの記事のポイントをまとめます。
- 営業の転職はタイミングが重要で、適切な時期を選ぶことで成功しやすくなる
- 営業職で限界を感じたら、無理をせず早めに転職を検討するべき
- 閑散期を狙うことで、スムーズな引き継ぎと円満退職が可能になる
- 年末は転職市場が活発になる時期で、求人の選択肢が増える
- 転職前に「なぜ辞めたいのか」を明確にし、冷静に判断することが重要
- 体調やメンタルの状態が悪化しているなら、転職を優先した方が良い
- 転職先を決めてから退職することで、焦らずに次のキャリアを築ける
- 営業職の転職は難しい面もあるが、戦略次第で成功しやすい
- コンサル・IT・人材・不動産・金融など、営業経験を活かせる業界は多い
- 転職市場の動向を把握し、自分の強みを活かせる業界を選ぶことが大切
- 転職エージェントを活用することで、効率よく希望の転職先を見つけられる
営業職からの転職は、単なる職種の変更ではなく、キャリアを飛躍させる大きなチャンスとなります。営業で培った交渉力や提案力は、多くの業界で求められており、適切な転職先を選ぶことで収入や働き方の質を向上させることが可能です。
特に、IT・SaaS業界やコンサル業界、人材業界などでは、営業経験が強みとなり、未経験でも挑戦しやすい環境が整っています。また、不動産や金融業界では、成果報酬型のシステムを活かしながら、高収入を目指せる可能性もあります。
転職を成功させるためには、適切なタイミングを見極めることが重要です。ボーナス支給後や閑散期、年末などを活用しながら、スムーズな転職を計画しましょう。今の環境に限界を感じているなら、新たなフィールドに踏み出す絶好の機会かもしれません。
今こそ、新しいステージで理想のキャリアを築く一歩を踏み出してみませんか?
「今の会社に少しでも不満がある」「年収アップしたい」「ブラックから抜け出したい」…そんな方にはまずは気軽に転職活動してみることを強くおすすめします。
転職エージェントや転職サイトは無料で利用できますし、良い企業が見つからなければ活動を辞めるのも全然アリです。自分の市場価値を知り、キャリアの幅を広げることが重要です。
当サイトでは多数あるサービスから厳選したおすすめの転職エージェントや転職サイトをまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
\ 転職活動の第一歩!気軽に無料登録! /
\ 自分のペースで進めたい人向け! /




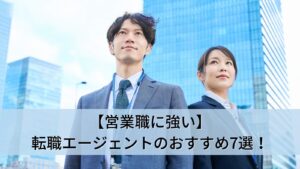


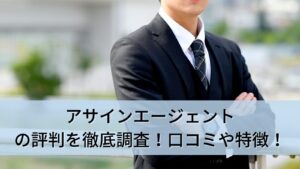
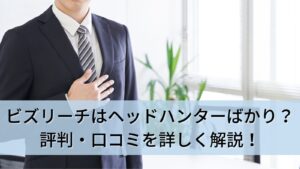

コメント